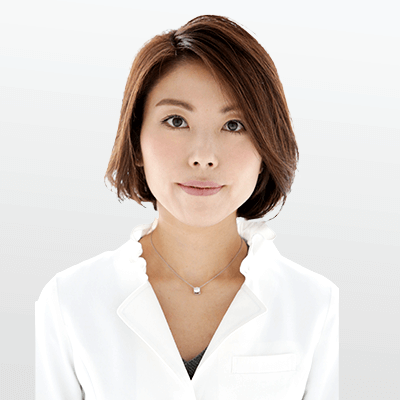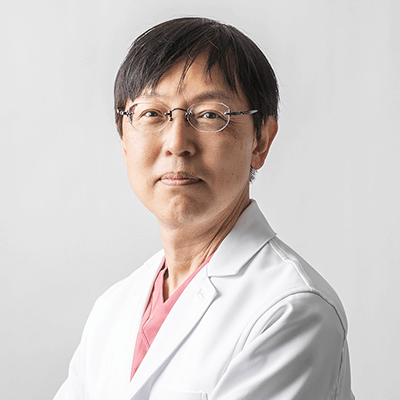いびきの原因やいびきをかきやすい人の特徴は?対処法もあわせて紹介!

寝る時のいびきがなかなか治らなくて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。隣で眠るパートナーを夜通し起こしてしまうほどの大音量でいびきをかく方から、自分のいびきの音で目覚めてしまう方まで、いびきによる弊害はさまざまです。
実は、いびきには明確な原因があり、特定の体型や生活習慣の方がいびきをかきやすいといわれています。この記事では、いびきの原因と、いびきをかきやすい方の特徴について解説します。質の高い睡眠を取るための方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
なかなか治らないいびきにはWクリニックオムのWナイトレーザーがおすすめ

夜寝ている時にいびきをかいてしまうという方は少なくありません。いびきをかいてしまうせいで「夜中に寝苦しくて起きてしまう」「人と一緒に寝ることができない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。いびきをかいていると、このような被害があるだけでなく、以下の健康被害が起きることもあります。
- 睡眠時無呼吸症候群
- 高血圧
- 糖尿病
- 心筋梗塞
- 脳卒中
- うつ病
- メタボ
- 認知症 など
いびきをかいていることで身体がだるくなり、健康被害を被ることがあるので、放置するのは大変危険です。そこでおすすめなのが、WクリニックオムのWナイトレーザーです。
従来のいびきレーザーは切開が必要で、痛みや出血がありました。また、ダウンタイムもあるので、なかなか気軽に受けられませんでした。Wナイトレーザーは従来のいびきレーザーと異なり、切開しないので、痛みや出血、ダウンタイムの心配をする必要はありません。また、施術は15分で終わるため、忙しい人にはもってこいです。
「いびきをすぐに治したい」「忙しくていびきを放置していた」という方は、ぜひ一度WクリニックオムのWナイトレーザーをお試しください。いびきを治すことで、人の目を気にせずに睡眠を取ることができ、快適な毎日を過ごせるようになるかもしれません。
大阪心斎橋のWメンズクリニックのいびき治療の詳細はこちら
いびきの種類

まずは、いびきの種類について見ていきましょう。
- 散発性いびき
- 習慣性いびき①単純いびき
- 習慣性いびき②睡眠時無呼吸症候群を伴ういびき
それぞれ詳しく解説していきます。
散発性いびき
偶発的にいびきをかくことがあります。これを「散発性いびき」といい、普段とは異なる身体の状態のときに起こります。
たとえば、過度な疲労感やアルコール摂取、風邪でリンパ節が腫れたり、アレルギーで鼻の通路が詰まったりするなど、特別な状況下で生じる一過性のいびきです。
習慣性いびき①単純いびき
いびきが日常の睡眠の一部となっている場合があります。これには2つのタイプが存在します。
1つ目は、無害で睡眠にも大して影響を与えない普通のいびきである「単純いびき」です。朝までぐっすり眠ることができ、日中の疲れや眠気をあまり感じないのが特徴です。単純いびきであれば、健康被害などを過度に心配しなくても良いでしょう。
習慣性いびき②睡眠時無呼吸症候群を伴ういびき
2つ目は、睡眠中の呼吸が一時的に休止することがある「睡眠時無呼吸症候群を伴ういびき」です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が何度も短時間停止する重いいびきです。睡眠時無呼吸症候群を伴ういびきは、睡眠の質を大きく低下させ、昼間の過度な眠気や持続する疲れの原因になります。
身体のさまざまな部位への酸素供給が不足するため、脳や身体へのリスクも高まります。医療機関での診断と適切な治療が推奨されます。
睡眠時無呼吸症候群について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて読んでみてください。
【要チェック】睡眠時無呼吸症候群とは?原因・症状・検査方法・治療法について
いびきのメカニズムは?
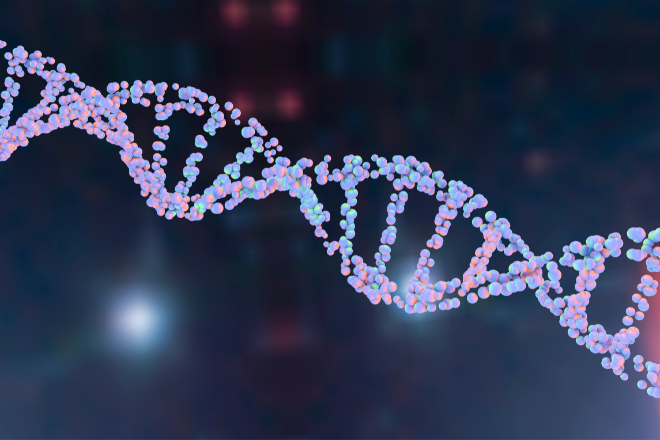
いびきは、息(空気)の通り道である喉や鼻の内部が細くなったときに起きます。この通り道が狭まると、そこを通る空気が喉や鼻を振動させ、それがいびきの音となるのです。
また、空気の通り道が狭まると酸素をうまく取り込めなくなり、体が足りない酸素を補おうとして、いびきが大きくなることがあります。
酸素の量が不足すると、普段は鼻で行なわれる呼吸が口からの呼吸に変わります。その結果、風邪にかかりやすくなったり、睡眠の質が落ちたりするかもしれません。
いびきをかきやすくなる原因

次に、いびきをかきやすくなる原因について見ていきましょう。
- 鼻づまり
- 疲労・ストレス
- 枕の高さ
- 口呼吸
- 肥満
- 飲酒(アルコール)
- 喫煙
- 風邪
- 睡眠薬
- 家族歴
- 女性ホルモンの減少
- 顔の骨格(小さいあご)
- アデノイド・扁桃肥大
それぞれ詳しく解説していきます。
鼻づまり
鼻づまりが常態化している方は、寝ている間に自然と口で息をしてしまいがちです。鼻がつまると、夜は特に副交感神経活動で鼻粘膜が腫れやすくなり、いびきをかいてしまいます。
花粉症やアレルギーで鼻の中が腫れがちな方はいびきをかく可能性が高いです。慢性の炎症があると、気づかないうちに悪化することもあります。日常生活では気付きにくい鼻詰まりが、就寝時に悪化し、結果としていびきにつながるのです。
両方の鼻づまりが苦しい場合は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
両方の鼻が鼻づまりが苦しくて寝れない!鼻づまりが苦しい原因と対処法は?
疲労・ストレス
身体が疲れていると、深く息を吸おうとして口呼吸になりがちで、それがいびきへとつながります。
また、疲労で筋肉が弛むと喉の狭まりを引き起こすため、いびきをかきやすくなります。
枕の高さ
枕が高すぎたり低すぎたりすると首の角度が不自然になり、気道が曲がることで空気の流れが悪くなります。
特に、枕が高いと頭が上がりすぎて、首が曲がり、それが気道の狭まりにつながります。あごが後ろに引けて気道が圧迫されると、いびきにつながるでしょう。
理想的な枕の高さは人それぞれですが、仰向けに寝たときに首・頭が背中と一直線になる高さが望ましいとされています。
口呼吸

寝ている間に口呼吸になると、いびきをかきやすくなります。口からの呼吸は気道の乾燥を招き、それがいびきの音を大きくする可能性があります。
疲れているときは脳が酸素を多く必要とするので、大きく口を開けて息をします。これがいびきを引き起こす原因となることも多いです。
肥満
肥満の方は首周りや喉の周りに脂肪が蓄積しており、これが気道を狭め、いびきを引き起こしやすくします。
さらに肥満が悪化すると、首周りだけでなく、内側の気道周辺にも脂肪が蓄積し始めます。この脂肪は気道を狭め、特に睡眠中の筋肉がリラックスした状態では、気道の崩壊や閉塞を引き起こしやすくなってしまいます。
その結果、振動していびきの音が発生する仕組みです。
飲酒(アルコール)
就寝前の飲酒は、喉の筋肉を緩ませてしまい、舌を落として気道を狭くします。その結果、息が細くなり、いびきの原因になります。
アルコールは睡眠の質も落とすため、睡眠の数時間前にお酒は飲まないのがおすすめです。
喫煙
タバコもいびきを悪化させる原因の1つです。タバコに含まれるニコチンやその他の化学物質は気道の炎症を引き起こすため、気道が腫れて狭くなってしまいます。これは、睡眠中にスムーズな呼吸を妨げ、いびきの原因につながります。
また、喫煙は睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクも高めます。睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、十分な休息を得ることができなくなるだけでなく、心血管疾患などの健康リスクも高めるため注意が必要です。
風邪

鼻づまりやのどの腫れは、風邪などの感染症の典型的な症状ですが、これがいびきの原因になることがあります。
風邪によるいびきは、風邪が治れば自然と解消されることが多いですが、慢性的な鼻づまりやアレルギーが原因の場合は治療が必要です。
睡眠薬
ストレスや不安が原因で、睡眠薬を使用する方が増えています。
睡眠薬を服用すると深い睡眠状態になるため、筋肉が通常以上にリラックスし、気道が狭くなります。また、呼吸筋の弛緩ももたらすため、結果的にいびきを誘発するでしょう。
家族歴
いびきは遺伝的要素を持つことが知られており、家族にいびき体質の方がいる場合、いびきをかきやすい体質になる可能性が指摘されています。
いびきの背後にある遺伝的な要因として考えられるのが、顔の骨格です。特に小さいあごや狭い上気道の構造は、いびきを引き起こす一因となりえます。
さらに、家族が共有する環境や生活習慣もいびきをかくリスクを高めることがあります。食生活、運動習慣、睡眠習慣などが影響することで、家族間でいびきをかく傾向が似る可能性があります。
女性ホルモンの減少
閉経を迎えた後、いびきをかきやすくなる女性も少なくありません。
更年期にさしかかると、女性ホルモンの1つであるプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌量が減少します。プロゲステロンには呼吸中枢を刺激し、上気道の筋肉を広げる効果があります。
その分泌量が減ることで、いびきが起きやすくなるとされています。
顔の骨格(小さいあご)
顔の骨格、特に小さいあごは、いびきをかきやすくする重要な要素です。
下あごが小さいと舌が後ろに落ち込みやすく、これが気道を塞いでしまう原因になります。
アデノイド・扁桃肥大
子どもに多くみられるのが、アデノイドや扁桃の肥大です。
これらが通常より大きくなると、鼻や喉の空間が狭まり、呼吸を妨げる結果、いびきを引き起こしやすくなります。
【性別別】いびきをかいてしまう原因

ここからは、性別別にいびきをかいてしまう原因を見ていきましょう。それぞれ原因が異なるため要チェックです。
男性がいびきをかいてしまう原因
男性がいびきをかいてしまう原因は以下のとおりです。
- 内臓脂肪型肥満になりやすい
- 首回りの構造上、筋肉が緩みやすい
男性は内臓脂肪型肥満になりやすいことがいびきをかいてしまう原因として挙げられます。内臓脂肪型肥満は、お腹周りに脂肪がつきやすい体型を指し、この脂肪が上気道の周りにも蓄積して、呼吸が阻害されやすくなります。これがいびきの発生につながるのです。
また、首回りの構造上、男性は女性と比較すると、筋肉が緩みやすいです。寝ている間に筋肉がリラックスし、特に舌の根元や喉の周囲の軟組織が気道を塞ぐように落ち込みます。
そのため、空気の通り道が狭まり、結果的にいびきの原因となることが多いです。
女性がいびきをかいてしまう原因
女性がいびきをかいてしまう原因は以下のとおりです。
- 妊娠
- 産前産後のストレス
- 更年期
産前産後は身体的、精神的に大きな変化が起こる時期です。ストレスや疲労が睡眠の質を下げ、いびきの原因になる可能性があります。また、子育てによる不規則な睡眠パターンも睡眠の質を落とし、いびきを引き起こしやすくします。
妊娠を経て体重が増加するのは、赤ちゃんの成長を支える正常な過程の一部です。しかし、適正体重を大幅に超えて体重が増加すると、気道を圧迫する脂肪が増え、それがいびきの原因になります。
いびきをかきやすい人の特徴

ここからは、いびきをかきやすい方の特徴を4つ紹介します。
- 男性
- 中高年の人
- 肥満気味の人
- 下あごが小さい人・首が短くて太い人
それぞれ詳しく見ていきましょう。
男性
先述のとおり、男性は女性と比べていびきをかきやすい傾向にあります。これは、男性の喉の周りの筋肉が緩みやすく、舌の根元が落ち込みやすいためです。
ホルモンの違いも影響を及ぼしており、女性ホルモンの1つであるエストロゲンには、気道の平滑筋を弛緩(リラックス)させ、気道を拡げる作用がありますが、男性はこのホルモンが少なく、いびきをかきやすいとされています。
中高年の人
中高年になると、筋力の低下が体全体に影響を与えますが、呼吸に関わる筋肉も例外ではありません。
寝ている間、特にリラックスした深い睡眠時には、舌の筋肉やのどの筋肉などが緩みます。これが気道の狭窄を引き起こし、いびきの原因になるのです。そのため、年齢とともにいびきをかく方が増える傾向にあります。
肥満気味の人
肥満はいびきのリスクファクターの1つです。体重が増えると特に首回りに脂肪が蓄積され、これが夜間の呼吸を妨げる主な原因となります。
肥満の方は、特に横になった状態での睡眠時に、脂肪組織が気道に圧力をかけ、気道が狭くなりやすくなります。気道が狭まることで、空気の通り道が制限され、結果として振動(いびきの音)が発生しやすくなります。
肥満が悪化すると、いびきの問題だけでなく、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクも高まります。
下あごが小さい人・首が短くて太い人
あごの構造はいびきに大きな影響を与えることが知られています。下あごが小さい方は、舌が後ろに落ちやすく、それが気道を塞ぐ原因になります。
また、首が短くて太い方も同様にいびきをかきやすいです。首回りの筋肉や脂肪が多いと、睡眠中に気道が狭くなりやすくなるためです。
いびきは放置しても大丈夫?

お酒を飲んだり風邪を引いているときにいびきが出るのは、一般的には気にすることではないでしょう。
しかし、病気がいびきの原因と問題です。そ気が原因だと、慢性的な睡眠不足に陥り、生活に悪影響を及ぼすこともあるので、気になる場合は病院に行くようにしましょう。
特に、睡眠時無呼吸症候群の中等度以上の症状がある場合、昼間の強い眠気が事故を招いたり、高血圧といった生活習慣病のリスクを上げたり悪化させる要因になる可能性があります。早い段階での医師の診断と治療が重要です。
子どものいびきには要注意

子どもがたまにいびきをかくときは、鼻づまりや疲れているとき、寝ているときに変な姿勢をしているときなどがあります。このくらいであれば、特に心配することはないでしょう。
しかし、毎日のようにいびきをかいているのであれば、気を付けた方が良いかもしれません。いびきでぐっすり眠れなくなることで、昼間も落ち着かなかったり、集中できなくなったりする可能性があります。
睡眠不足が体の成長に必要なホルモンにも影響を与える可能性があります。長期間にわたっていびきが続くようであれば、クリニックや病院で相談してみると良いでしょう。
いびきの対処法

疲れが溜まっているときは、脳が酸素を必要として、口で呼吸することが多くなります。そうすると空気がのどを多く通るため、いびきが出やすくなります。
お酒やタバコも、いびきを引き起こしやすくします。もしいびきが気になるようであれば、疲れをしっかりと癒し、お酒やタバコはほどほどにすると良いでしょう。
また、いびきをすぐに何とかしたい場合、いびき防止グッズを使用するのもおすすめです。いびきを軽減するための色々な種類のグッズがあるので、自分に合ったものを選んでみましょう。
普段の生活に気を付けて、良い生活習慣を心掛けてみてください。以下の記事では、いびき対策についてさらに詳しく解説しています。
自力でできるいびき対策やいびき対策におすすめのグッズは?原因と合わせて徹底紹介!
まとめ

いびきをかきやすくなる原因にはいくつかありますが、日常生活のちょっとした習慣がいびきを引き起こしているかもしれません。
いびきは睡眠時無呼吸症候群(SAS)などのさまざまな健康問題を引き起こすこともあるため、慢性的ないびきには注意が必要です。いびきが頻繁に発生し、日中の疲れや集中力の低下といった症状もみられる場合には、医療機関への受診をおすすめします。
なかなか治らないいびきにはWクリニックオムのWナイトレーザーがおすすめ

夜寝ている時にいびきをかいてしまうという方は少なくありません。いびきをかいてしまうせいで「夜中に寝苦しくて起きてしまう」「人と一緒に寝ることができない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。いびきをかいていると、このような被害があるだけでなく、以下の健康被害が起きることもあります。
- 睡眠時無呼吸症候群
- 高血圧
- 糖尿病
- 心筋梗塞
- 脳卒中
- うつ病
- メタボ
- 認知症 など
いびきをかいていることで身体がだるくなり、健康被害を被ることがあるので、放置するのは大変危険です。そこでおすすめなのが、WクリニックオムのWナイトレーザーです。
従来のいびきレーザーは切開が必要で、痛みや出血がありました。また、ダウンタイムもあるので、なかなか気軽に受けられませんでした。Wナイトレーザーは従来のいびきレーザーと異なり、切開しないので、痛みや出血、ダウンタイムの心配をする必要はありません。また、施術は15分で終わるため、忙しい人にはもってこいです。
「いびきをすぐに治したい」「忙しくていびきを放置していた」という方は、ぜひ一度WクリニックオムのWナイトレーザーをお試しください。いびきを治すことで、人の目を気にせずに睡眠を取ることができ、快適な毎日を過ごせるようになるかもしれません。